このページでは、コンビニの店舗において電子棚札が導入された事例について紹介しています。電子棚札の導入を考える際の材料としてご活用ください。
現代日本で暮らす人々にとって、24時間365日営業を基本とするコンビニはもはや生活インフラの一部となっており、コンビニはある意味で日本経済の象徴と言えるでしょう。
反面、定休日や閉店時間のないコンビニでは常に人員を配置しておかなければならず、超少子高齢化によって慢性的な人材不足が深刻化している日本では、高齢のコンビニオーナーが休みなく働き続けるといった過酷な環境も発生しています。
そのためコンビニ経営において、少しでも業務の省力化や効率化に貢献するシステムの導入やDX化といった取り組みは、持続可能なコンビニ経営を叶える上で重要な課題となっています。
コンビニの店舗へ電子棚札を導入するメリットとして、最も大きなものが値札の交換や準備といった作業を省略できるという点です。
電子棚札はオンラインで本部とシステム連携しており、本部が対象商品の値段を変更すれば、そのまま各店舗でも商品の値札の表示が自動的に変更されます。これにより従業員は接客やその他のコア業務へ注力できるようになり、希少なヒューマンリソースの活用方法を適切にマネジメントできることが重要です。
電子棚札は表示の自動切り替えの他にも色々な活用法を検討することができます。
電子棚札の活用法の1つが、デジタルサイネージとしての活用法です。
サイネージとは店舗の内外などに設置する広告宣伝用のディスプレイやタブレットであり、任意の映像や情報を画面へ表示させることでプロモーションへ役立てることができます。
電子棚札も効率的に期間限定商品をアピールできるため、販売促進を活性化するために有用です。
電子棚札では価格の表示方法などを任意に調整できるため、例えば単品価格とお得なセット価格や割引価格などをそれぞれ表示して、消費者への訴求効果を高めるといった使い方も考えられます。
また、ランチタイムや週末など特定のタイミングにピンポイントで情報を提供し、消費者へリマインドしていけることも強みです。
消費者にとって購買意欲に影響するポイントは価格だけではありません。使用されている原料や摂取カロリー、原産地といった様々な情報を電子棚札で表示することで、価格だけではない様々な付加情報を提供し、消費者の購買意欲やニーズへダイレクトにアプローチしていけることは大きな強みです。
またコンビニであっても地域ごとの特色や魅力があり、例えば地元産の商品をアピールすることで地産地消の促進や、持続可能な地域社会への貢献といったメリットを追求することもできるでしょう。
その他にもアレルギー表示などを拡充させることで安全面への配慮も強化できます。
日本全国にコンビニチェーンの「セブンイレブン」を展開するセブン-イレブン・ジャパンでは、219年12月から東京の一部店舗において電子棚札の試験導入をスタートさせました。
慢性的な人材不足が日本経済における課題となっている中、値段の張り替え作業をオートメーション化することで業務の効率化や省力化に貢献し、人手不足に対応するといった目的を掲げて導入された形です。
導入場所は千代田区にある直営店が対象となり、状況を分析しながら順次他の店舗への導入を計画しています。
※参照元:日本経済新聞「セブンが電子値札導入 まずは東京・千代田の店舗に 作業負担軽減」(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53458080X11C19A2HE6A00/)
電子棚札はコンビニの従業員にとって日々の業務の負担を軽減し、作業を効率化して人材不足などを経営課題にも対応できるだけでなく、コンビニを利用する消費者にとってもお得な情報や栄養成分などをチェックしやすくなるため便利です。
このサイトでは、現場の課題を解決に導く電子棚札を提供している会社をまとめました。各社の電子棚札の特徴や機能をしっかりチェックしたうえで、自社に合ったものを選んでください。
このサイトでは、コンビニだけでなく他の業種の導入事例についても紹介しています。他の業種では電子棚札をどのように活用しているのか気になる方は、以下のリンクからぜひ他の業種の導入事例についても参考にしてみて下さい。
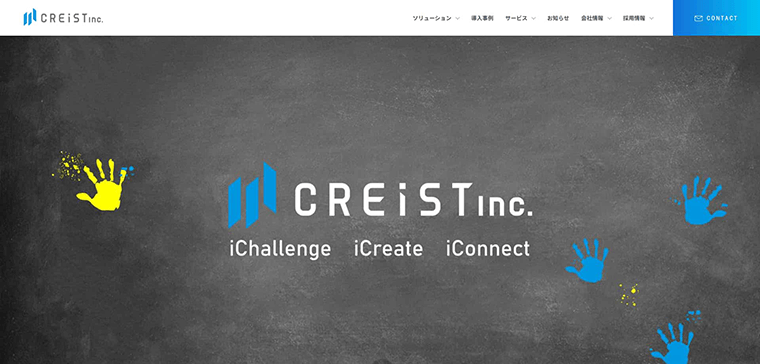
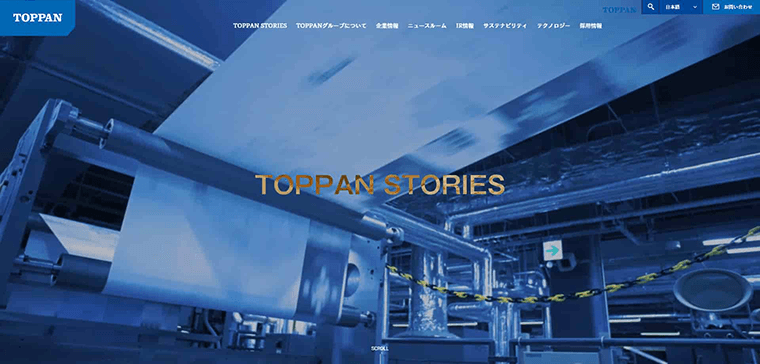
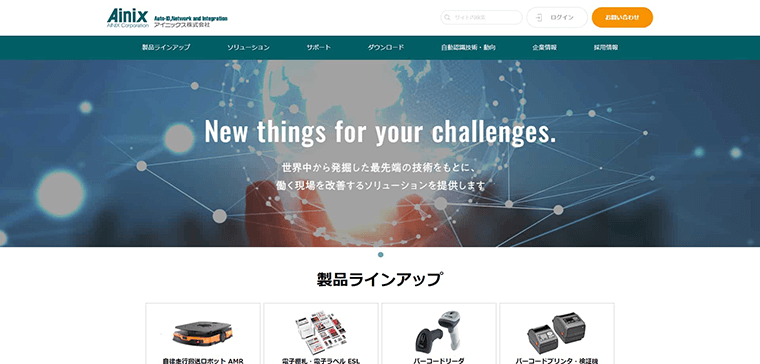
※階数の多い大手家電量販店ビックカメラで、全店約50店舗(※)の電子棚札を稼働させた実績あり。参照元:CREiST公式HP(https://www.creist.co.jp/casestudy/biccamera/)2024年11月15日調査時点